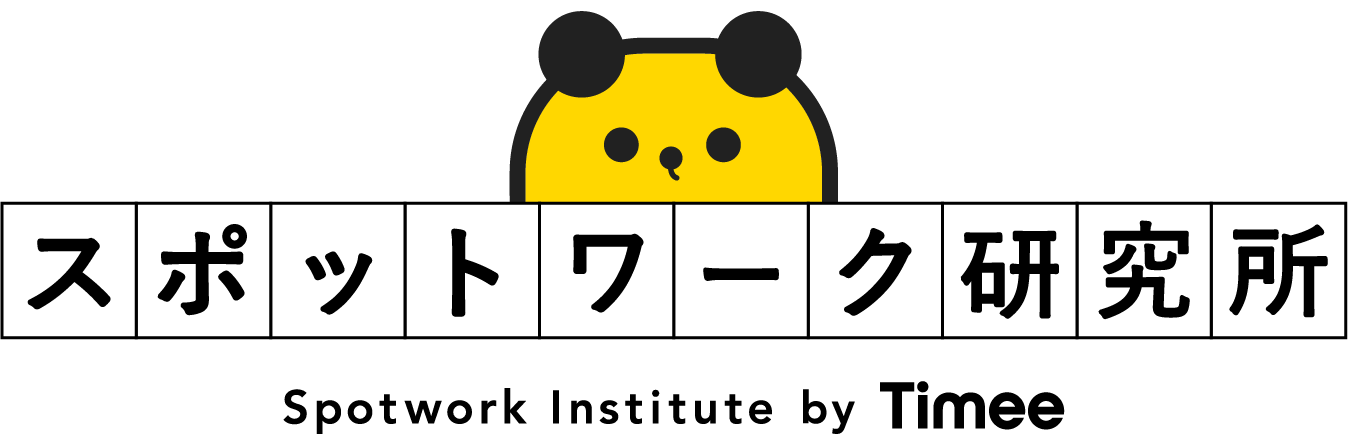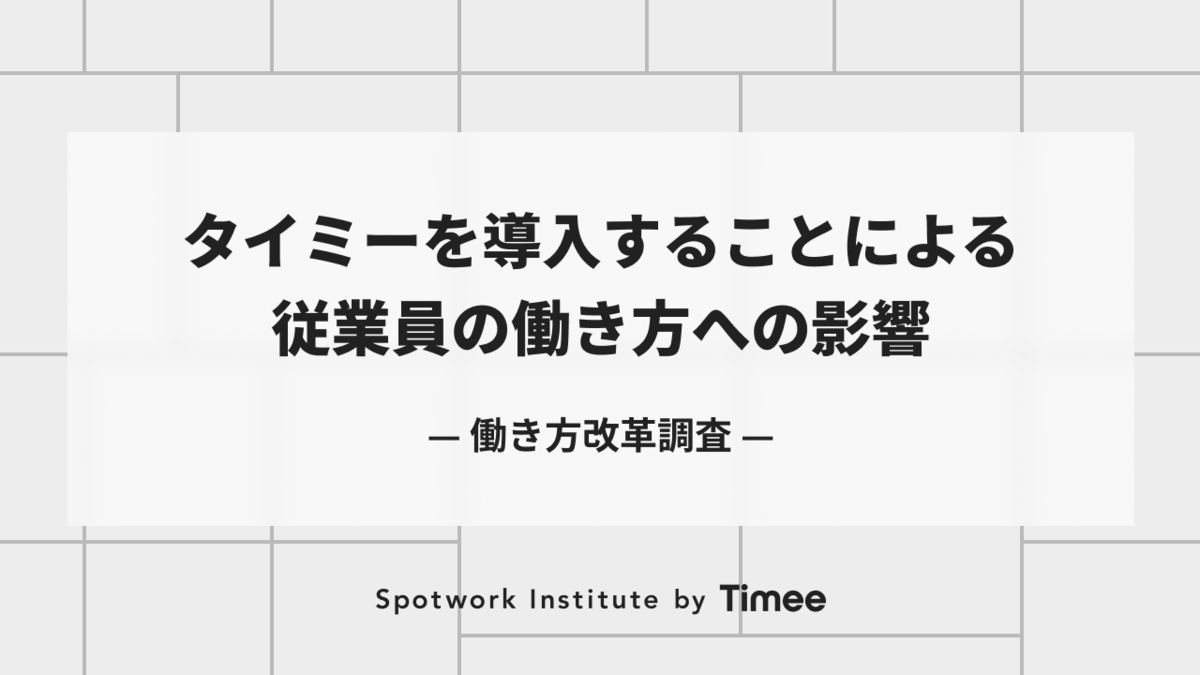- 若年無業の主要因は「自信のなさ」「履歴書・面接ハードル」
- タイミーが若年無業者の「経験の穴」を埋める
- 見学の仕組み、アルムナイネットワーク…...。タイミー活用の手応えと、より安心安全を実現するアイデア
- 支援者ボトルネックを超え、社会的な認証も得ていきたい
- 行政・支援機関と連携し、人生の可能性を広げるインフラへ
- おすすめ記事
「若年無業者」とは、15歳から39歳の非労働力人口のうち、通学も家事もしていない人を指す言葉。2021年時点で、その数は全国に約75万人いるとされています(子供・若者白書より)。少子高齢化による労働力不足が進むなか、若年無業者が社会とどうつながり直すかは、個人の人生にとっても、社会全体にとっても重要なテーマです。
こうした問題に、20年にわたって向き合ってきたのが、認定NPO法人育て上げネット代表の工藤啓さん。内閣府、厚生労働省、文部科学省などの委員を歴任し、制度と現場の両面から若者支援を続けてこられました。そんな工藤さんは、現在、若者の就労支援のなかでタイミーを活用。「NPOや公共の支援ではカバーできない部分を、スポットワークが埋めてくれる」と言います。
実際に、育て上げネットはどのようにタイミーを活用しているのでしょうか。そこから見えてきた手応えや課題、そしてこれからの若年無業者支援のかたちについて、タイミースポットワーク研究所の石橋孝宜、山口眞司がお話を伺いました。
1977年、東京都出身。認定NPO法人育て上げネット理事長。成城大学中退。Bellevue Community College卒業。内閣府、厚生労働省、文部科学省など委員歴任。「無業社会」など著書多数。金沢工業大学客員教授。プライベートでは、長男次男、双子の三男四男の四児の父。
中央大学卒業後、コンサル、ウェディング、飲食会社での現場・人事・事業経営者を経てタイミーに入社。入社当初より求職者・求人者双方の利便性を高めるべく、プロダクト設計に寄与。人事や現場の経験からユーザーが使いやすいサービス設計に寄与するとともに、コーポレート、事業それぞれの責任者を経てスポットワーク研究所所長となる。
早稲田大学卒業後、厚生労働省に入省。若年者雇用、派遣労働者の同一労働同一賃金、雇用関係助成金の企画などに携わる。2024年より株式会社タイミーに入社。地方自治体等と連携し、タイミーを活用した「就職困難者の就労支援」、「キャリア教育」、「災害復興対策」などのプロジェクトを担当。
若年無業の主要因は「自信のなさ」「履歴書・面接ハードル」
——まずは工藤さんに、育て上げネットの設立背景と若年無業者の現状について伺います。
工藤啓さん(以下、工藤さん):育て上げネットは約20年前、当時「働きたいけど働けない」若者が80万人ほどいる中で、若者の社会復帰を支援する目的で立ち上げました。現在では高校や少年院などとも連携し、年間3万人ほどの若者と関わっています。無業の若者は毎年およそ2,000人が新規で相談に来ています。
この20年間でわかってきたことのひとつは、若年無業者の割合は景気に左右されにくく、常に「若者人口の2%程度」存在するということです。もうひとつは、「働く自信がない」ことが大きな壁になっている点です。2013年に私たちと立命館大学で行った調査(『若年無業者白書 - その実態と社会経済構造分析 -』)では、無業者の約半数がこの理由を挙げていました。自信をつけるには働く経験が必要ですが、働くにはまず自信が必要という矛盾があります。

石橋孝宜(以下、石橋):職業体験やインターンでその自信をつけるのが大事ということですね。
工藤さん:たしかに有効な方法のひとつですが、無報酬の体験では経験できる範囲も機会も限定的で、「働く自信問題」の根本解決にはなりません。
山口眞司(以下、山口):一方で、働く自信はあるけれど、働けないという人もいるのでしょうか?
工藤さん:はい。就職活動では「履歴書」と「面接」が大きな2つの大きな壁になっています。無業期間があると履歴書に書ける経験が少なく、空白期間を問われると答えづらい。さらに、面接が苦手な人も多く、2枚の壁に阻まれて無業に戻ってしまうケースが多いのです。
——15〜39歳の中で、特にどの年代層の方が相談にいらっしゃるんですか?
工藤さん:今は10代、20代の相談者が増えています。それは支援の選択肢がスマホなどで調べやすくなり、アクセスのハードルが下がったことも起因しています。
また、社会全体に「早いうちに社会資源とつながることが重要」という認識が広がってきたことも影響しています。自治体、学校、NPOなど支援者のあいだでも共通した理解があり、早期支援の機会が増えてきた結果、10代、20代の層が可視化されやすくなっているのだと思います。
——「無業者=働こうとしない、もしくは働けない人」といったイメージを持つ方もいるかもしれません。実際に接してきたなかで、どのような方が多いと感じていますか?
工藤さん:自信がなく一歩踏み出せていないものの、働く力を備えている人は多い印象です。特に離職して間もない人なら、すぐに働ける力を持っている場合もあります。それに、受け入れてくれた会社に対する恩義を感じているため、就労後に長く続ける人も多いんです。ただ、正社員登用や昇進といった話になると、急に辞めてしまうケースもある。そこが難しいところです。
石橋:働きやすい環境や条件が揃えば、活躍できる方々も多いと。
工藤さん:はい。しかし、日本の職場では、人間関係における「構いすぎ」が負担になることもあります。仕事上のコミュニケーションは問題ないのに、雑談や飲み会のような“仲間感”が求められる空気に苦手意識を持つ人も多い。そういった場面では、本来の力が発揮しづらくなってしまいます。
石橋:そのような方々が力を発揮できる環境が、もっと広がっていくと良いですね。
工藤さん:まさにそうです。今は人口が減って若者の数も増えません。かつて「ニート」と揶揄されていた層も、いまや人手不足に悩む中小企業から切望される存在になっています。労働市場から見ても、彼らは十分に貴重な人材です。

——働きたい人と人材を求める企業の橋渡しも、育て上げネットの役割なんですね。ただ、働き始めてもうまく馴染めないケースもあるかと思います。そうしたときは、どうサポートしているんでしょうか?
工藤さん:信頼関係のある企業の場合は、話を聞いて現状を整理したり、認識のズレを解消します。また、職場とは異なる存在として居場所を提供し、働き続けることをフォローします。
山口:働き始めたばかりの人が仕事上のネガティブなフィードバックを受けたことで、「やっぱり働きたくない」となってしまうケースもありそうですね。支援者がいてくれるのは心強いと思います。
工藤さん:フィードバックの解釈や受け取り方を変えられれば、前向きに働き続けられることもあります。とはいえ、その職場が本当に合っていないと感じたら、別の選択肢を一緒に検討することもあります。どちらかに偏らず、中立的に寄り添う姿勢が大切だと思います。
タイミーが若年無業者の「経験の穴」を埋める
——若年無業者の課題を踏まえたとき、タイミーはどのように貢献できるのでしょうか?
工藤さん:若年無業者の中には、学校に通えなかったり、卒業後すぐに無業になった方がいます。彼らは、上司との業務上のやりとりや、友達との集団行動といった経験が乏しい。それを「経験の穴」と呼びますが、タイミーのようなスポットワークは、経験の穴を埋める一助にもなり得ます。これまでNPOや公共の支援ではカバーしきれなかった部分に、柔軟に入り込める可能性があるんです。
石橋:私たち自身、どこまで貢献できるかをまだ探っている段階ではあるのですが、そう言っていただけて光栄です。
工藤さん:貢献の幅は大きいと思います。書類選考や面接がないという特徴は、私たちが関わる若者にとっての“敷居の高さ”を下げてくれる働き方なので、働くきっかけになるのはもちろん、昇進に抵抗のある方にとっても、副業的にスポットワークを活用することで収入を安定させたり、キャリアを柔軟に設計したりする助けになります。
山口:支援を受けている方の中には「好きなことを仕事にしたい」という方も多いと聞きました。フリーランスなどの仕事に挑戦する一方で、収入への不安もある。スポットワークと好きな仕事を組み合わせることで、生活を支えながら挑戦を続けることができそうです。

——タイミーのようなスポットワークが就労の入り口にもなり、就労後の生活の支えにもなると。
工藤さん:加えて、孤立や孤独を緩和できる可能性を秘めていると思います。私は毎年3月末に「 4月1日から居場所を失ってしまう方へ」というブログを書いているのですが、今年はその中で、スポットワークの利用を勧める文章を書きました。
家庭以外の居場所が少ない日本では、学校を卒業してすぐに無業になると、居場所を失い、孤独・孤立にもつながります。そんなとき、2時間でも働くことで気持ちが前向きになるかもしれないよ、という内容です。
——仕事を通じて人と関わり、感謝される経験が、社会とのつながりや自己肯定感につながるんですね。
工藤さん:その通りです。心身に不調を抱えている方にとっても、週1回、数時間から始められる働き方は、無理なく社会と関わる第一歩になると思います。
見学の仕組み、アルムナイネットワーク…...。タイミー活用の手応えと、より安心安全を実現するアイデア
——育て上げネットでは、実際にどのようにタイミーを活用しているのでしょうか?
工藤さん:法人本体と、厚生労働省(都道府県労働局)からの受託事業として運営している地域若者サポートステーションの両方で活用しています。働きたい若者との個別相談のなかで、スポットワークという選択肢を紹介するんです。ハローワークや職業体験、フリマアプリなど他の手段と並べて、その人に合った方法を提案しています。スポットワークの選択肢としてタイミーを紹介していますが、職場の選択肢も多く、直接雇用契約が結ばれる点で、安心して紹介できる存在です。
山口:スポットワークを就労支援の一つのツールと位置付けているわけですね。選択肢として勧めやすい一方で、逆に「まだスポットワークを勧めないほうがいい」と判断することもあるのでしょうか?
工藤さん:あります。準備が整わないまま有償で働くのを勧めてしまうと、本人にも事業者にも負担がかかってしまう。そう判断した場合は、無償の職業体験など別の選択肢を先に提案します。
あとは、料金やギガの問題で、スマホを持っていない、もしくは使えない子たちにもスポットワークは勧められません。アプリを入れることに抵抗があったり、知らない職場に行くこと自体が不安という若者もいます。そのような人へのケアが必要なことを前提として、スポットワークは就労に向かう支援のツール、選択肢として利用できます。
山口:就労支援は、いきなりゴールを目指すのではなく、段階を踏んだ支援が必要と認識してます。スポットワークは、無償の職場体験などの支援を受けた人の次のステップとしても位置付けられそうですね。

——「知らない職場に行く不安」を下げるために、どんな工夫が考えられますか?
工藤さん:グループで働けると、安心感がぐっと高まると思います。また、「見学タイミー」とでも言うのでしょうか。職場の雰囲気や仕事内容を10分ほど見学して、できそうであればそのまま働けるような仕組みがあると、安心して一歩を踏み出しやすくなると思います。
石橋:いいですね。タイミーでは事前にマニュアルを見てもらうことで「どんな仕事なのか」をイメージしてもらう取り組みを行っています。事前に動画で雰囲気を伝えるのはいかがでしょうか?
工藤さん:効果はあると思います。しかし、動画や画像になると「元気でアットホームな職場」を演出してしまう企業も多く、それはかえって逆効果になることも。必要なのは、もっとリアルな職場像です。
山口:タイミーの「相互評価」の機能は、職場の雰囲気を知るヒントになりますか?
工藤さん:参考にはなりますが、書き手の背景が見えない点には注意が必要です。たとえば、「楽しく働けた!」という声も、自分とは背景や属性が違いそうな人の感想だと、あまり響かないかもしれません。
「長く働いてなくて不安だったけれど、安心して働けた」なら、自分にも合いそうだと感じられますが、そうした背景をあえて書くのには抵抗があるとは思います。お世話になった企業の印象を悪くすると感じて、書かない人も多いのではないでしょうか。
——「どんな職場か」だけでなく、「どんな背景の人が」働いたのかもわかるといいと。似た境遇の人がいることは安心感につながりますよね。
工藤さん:実際、ある会社では、育て上げネットの支援を受けた方が40人ほど就職していて、全社員の4分の1を占めているんです。やはり安心感が違いますよね。「タイミーアルムナイ」という言い方が適切かわかりませんが、「タイミーを通じて就労した人たちがこれだけいる」ということが可視化されれば、初めて働く方にとっても安心かもしれません。

——タイミー側の目線から見て、支援を受けている方が働く経験のひとつとしてタイミーを利用しやすくするために、何か工夫できることはありますか?
石橋:ポイントは、企業側が「仕事の切り出し」を工夫することだと思います。たとえば、兵庫県三田市では、ひとり親の方が働きやすい時間帯の仕事を提供する事業者が、自らを「ひとり親家庭応援企業」と自治体に宣言してもらう取り組みを行う予定です。
同じように、若年無業者の方に向けても、働きやすい時間帯や取り組みやすい仕事内容に分けて仕事を設計できれば、より利用しやすくなるはず。事業者の方々と協力していきたいところです。
工藤さん:社会とのつながりを失った若者は、人目を避けて夜型の生活になることもあります。もともと朝が苦手で夜が得意なひともいるでしょう。夜型を生かすにせよ、少しずつ生活サイクルを朝型に改善していくにせよ、深夜帯に働ける職場があるのは、きっかけをつかみやすいと思います。
石橋:物流やコンビニなどは、深夜帯の求人もたくさんあります。
工藤さん:タイミーを活用すれば、徐々に朝型に移行できるかもしれません。以前の支援は「まず夜型生活を直そう」というアプローチでしたが、これはなかなか難しいんです。最初は深夜2時からの仕事をしてみて、支援者がサポートしながら、「次は24時から」「次は22時から」と、少しずつ慣れさせていくのがいいと思います。それができるのは、柔軟に働く時間を変えられるスポットワークならでは。
山口:柔軟に働く時間を変えられる点は、就労支援の中でタイミーを使うポイントになりそうですね。工藤さんがおっしゃった「時間帯の調整」のほかにも、「就労日数の調整」もできると考えています。「今週は週1日だけ働き、次の週は週2日働き、その次の週は休息をとる」などの働き方もタイミーであれば可能です。
また、このような柔軟な働き方を通じて、自身がどの程度の時間・日数・通勤距離であれば働けるのかを把握し、本格就労の仕事選びに活用していくこともできます。
支援者ボトルネックを超え、社会的な認証も得ていきたい
——実際にタイミーを利用された方の反応についても伺いたいです。長期雇用につながった事例もあるそうですね。
工藤さん:タイミーで働いた職場に長期採用された方もいますし、自信がついて別の場所で就職した人もいます。よく聞く声としては、「面接がないのが良い」というものですね。支援を受けている方のなかには、働く力は備えているけれど面接に抵抗感を持つ人も多い。「勤務日数を自分で調整できるのがありがたい」というものもあります。体調面などを考慮しながら、徐々に勤務日数を増やすことができます。
また、事業者からは、「地域若者サポートステーションのような公的支援機関からの紹介だったので、安心して受け入れられた」という声もありました。
山口:ひとり親の支援事例ですが、本格就労の前にタイミーを使うことで、実務経験を得られたという声を聞いたことがあります。専業主婦の期間が長くブランクがあったが、タイミーで働くことで、書類選考や面接で実務経験としてアピールできたという声もあった。本格就労に向けた採用選考の対策でも、タイミーは貢献できると思います。
——一方で、利用が進むなかで見えてきた課題もあるのではないでしょうか?
工藤さん:大きな課題は、「支援者ボトルネック」です。スポットワークは新しい働き方ですので、多くの支援者はスポットワークを知らない、または知っていても利用経験がないでしょう。
少なくとも育て上げネットの職員で経験していたのは、ほんの一部だけでした。それも、若者たちのためになりそうかという視点で「やってみた」ケースです。支援に活用するには、まず支援側がその価値を理解している必要があります。
石橋:プラットフォーマー側にできることはありそうでしょうか?
工藤さん:ぜひ、支援者向けに説明する機会を一緒に設けていければと思います。また、スポットワークの活用を「就労支援のプロセスに組み込んでよい」ということを、社会的に認められる流れにしていくことも大切ですね。
——「社会的に認められる」とは、どういうことなんでしょうか?
工藤さん:これまで就労支援の公共事業において、「スポットワークを使ってよい」と明示された仕様書は見たことがありません。すると受託した組織は、導入しても「公費の対象外」と言われる可能性があり、支援のなかで手を出しにくい。
一方で、令和7年度から、厚生労働省の地域若者サポートステーションの事業において「1週間の所定労働時間が20時間未満又は31日以上の雇用見込みがない求人」を活用した就労支援の項目が新たに追加されました。スポットワークの活用が否定されることはなくなってきています。
山口:地域若者サポートステーションの相談窓口は、全国に177箇所ありますが、ここでのリアルな事例や利用者の声を蓄積していければ、全国へ一気に広がる可能性もあります。
工藤さん:ほかにも、全国700箇所ほどある生活困窮者向けの就労準備支援事業所など、展開できる場はあります。そうした場所の支援内容は、履歴書の書き方や面接対策が中心なのが現状。でも、それを飛び越えた支援方法として、スポットワークが認められるようになると大きいですね。

——積み重ねた事例をもとに、国や行政から認められる状態を目指していくのですね。他に、社会実装のためのアプローチとして考えられるものはありますか?
工藤さん:教育機関と連携する方法も考えられます。実は高校では、職場体験やボランティア、インターンやアルバイトを単位として扱っている学校も出てきています。生徒のなかにはアルバイトをしなければならない環境の若者がいるのも事実です。しかし、そのなかには自信がなかったり、どのアルバイトが向いているのかまだわからない方もいます。
人手不足に悩む地元の中小企業からすると、この仕組みを活かして、在学中から生徒が働いてくれれば助かりますし、卒業後もそのまま入社するという“縁故採用的なルート”を活用できる。そうしたかたちで、地域、学校、企業にとってメリットがある仕組みを構想している学校もあります。
石橋:面白い構想ですね。
工藤さん:ただ、高校生が働けるのは放課後の16時〜19時の3時間程度。その時間に合った仕事を切り出せる企業が少ないのが課題です。それができれば、その仕組みのなかにタイミーを導入することもできると思います。
石橋:特定の地域を選んで、高校・自治体・支援機関と連携しながら実証事例をつくってみたいですね。タイミーには「18歳以上の高校生のみ利用可能」という制約もありますが、その中でどこまでできるかチャレンジしたいです。
工藤さん:誰もがSNSで情報を検索したり、公的機関に問い合わせたりするわけではありません。また、信頼できる情報かどうかを自分で判断するだけの経験が不足していることもあります。だからこそ、すでに接点のある学校などを起点に、「ラストワンマイルに届くモデル」を築けると、より現実的な支援につながると思います。
行政・支援機関と連携し、人生の可能性を広げるインフラへ
——構想をかたちにして、きちんと届け切るところまでしていくと。終盤ですが改めて、タイミーがこうした社会課題に取り組む意義を教えていただけますか?
石橋:タイミーは「面接や履歴書なしですぐに働ける」という手軽さが注目されがちですが、本質は「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」ことにあります。代表の小川が1社目の会社を閉じて自信を喪失していたなか、コンビニでアルバイトをした際に、「自分の時間が誰かの役に立つ」ことを実感した経験から、このサービスは生まれました。
どのような状況の方でも、仕事を通じて自分に合う働き方に出会い、人生の可能性を広げていける。そんな世界を実現したいというのが、タイミーが若年無業者の方の就労支援に取り組む理由です。

山口:若年無業者の方に限らず、ひとり親や生活困窮者、ヤングケアラーなど、さまざまな支援が必要な方々に向けて、自治体や支援機関と連携しながら取り組みをしてきました。就労支援の中でタイミーの働き方を取り入れることは相性がいいと考えています。
これからも、日々現場に向き合っている支援者の方々と力を合わせながら、就職困難者が抱える課題の解消にタイミーがどう貢献できるかを、一緒に模索していきたいと考えています。
——工藤さんは、今後のタイミーに期待されていることはありますか?
工藤さん:タイミーを通じて「この職場はよかった」と思える経験が、一人でも多くの若者の中に残ってほしいと思っています。よい経験の積み重ねは、働く自信にもつながりますし、「こういう企業なら安心できそう」といった目利き、判断材料が身についてきます。働き手が企業を見極め、選ぶ側にまわっていければ、人をぞんざいに扱う企業も自然と減っていくのではないでしょうか。
石橋:どのような企業が「働き手に選ばれているのか」を見える化していきたいですね。実際、国や政府の方も「ワーカーによる評価」に関心を持ってくださっている。働き手に優しい企業を表彰する制度などができないか考えています。
工藤さん:企業の実態が見えると同時に、「働いたことで人生が前に進んだ」という声がもっと増えてくるといいですよね。「不安だったけれど、この職場で少し前向きになれた」というような体験談が、次の誰かの背中を押す力になるはずです。

——タイミーのようなスポットワークの仕組みを支援の選択肢に加えたいと考える自治体や支援機関も増えていると思います。そうした方々に向けて、何かヒントや提案があれば教えてください。
工藤さん:支援者の方々は、日々現場と向き合っていて、本当にご多忙だと思います。ただ、そのなかでもなんとか時間を見つけて、新しい働き方に一度触れてみてほしいです。
自身でタイミーをダウンロードして、2時間だけでも働いてみる。たったそれだけで、「この子に紹介できそうだな」と顔が浮かぶこともあるはずです。支援の幅を広げる意味でも、まずはご自身から体験してみていただきたいです。ただ、支援者にも不安がありますので、タイミーさんと一緒に広く機会提供の仕組みをつくれたら嬉しいです。
山口:タイミー社だけでは、若年無業者の方などに直接リーチすることはできません。だからこそ、若年無業者の方などが実際に相談をしている自治体や支援機関のみなさんと連携していくことが欠かせない。現場と向き合っている方々の力をお借りしながら、タイミーの可能性を広げていければと思っています。もし関心を持っていただけたら、ぜひお声がけください。
石橋:引き続き、“人生の可能性を広げるインフラ”として、タイミーを社会に根づかせていくことを目指していきます。より働きやすい仕事や、安心して働ける職場を少しでも増やしていくこと。そのために、事業者とも、支援機関とも連携しながら、より良い仕組みをつくっていきます。
(取材・執筆:佐藤 史紹、撮影:村井香)